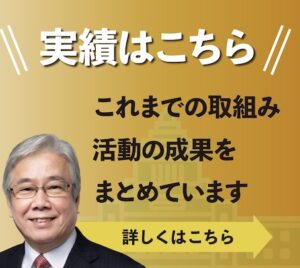慢性の痛みの対策と課題
4月16日、慢性の痛み対策議員連盟の打ち合わせ会議に参加しました。慢性の疼痛とは、「治療に要すると期待される時間の枠を超えて持続する痛み」(IASP国際疼痛学会 2020年)とされていますが、条文案では、「進行性かつ持続性の痛みやその治療が困難でかつ生活に著しい支障がある程度のもの」と書き加えられています。
難治性慢性疼痛により、自身の健康上の問題だけでなく,他者に理解されないことによる社会的孤立など重大な困窮状態にある方々に対して、医療のみならず個としてのその人を支える体制づくりを目的として法制化に取り組んでいます。その過程で派生する想定外の様々な課題をひとつずつ丹念に解決し、内外に対して理解を得る地道な活動を始めてすでに10年。

慢性の痛みは、当事者の生活の質を著しく低下させ、個人の尊厳を損なう要因となったり、本態が十分に解明されていないために適切な治療を受けられない場合が多くあります。私も議員任期当初からこの議連に関わっていますが、痛みは生体の警告信号とされつつも、痛みそのものが問題となるケースに私達リハビリ専門職は多く遭遇します。
何をやっても十分な効果が得られない、治療者として無力感にさいなまれることも少なくないのではないでしょうか。殊に慢性持続性疼痛に対しては、様々な分野の専門家が治療に参加する集学的医療アプローチが必要ですが、集学的痛みセンターは全国にAタイプ12施設、Bタイプ32施設があるに過ぎません。対して有病率は、成人人口の22.5%、推計患者数は約2,315万人に上るとの報告があります。
立法府で活動する医療人のひとりとして、社会保障関連すべての法案が血の通った温かい制度づくりに資するものであることを念願しつつ、当事者目線での発言をこれからも続けたいと考えています。誰にも理解されない痛みという困り事を抱えていらっしゃる方々にとって大きな希望、拠り所になるよう立法化に向けて、引き続き取り組んで参ります。




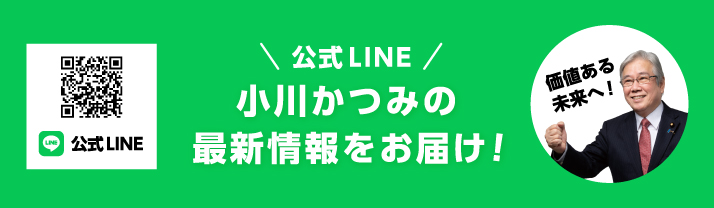


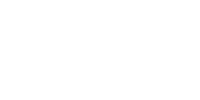
 前の記事へ
前の記事へ 次の記事へ
次の記事へ